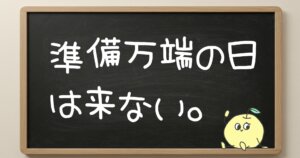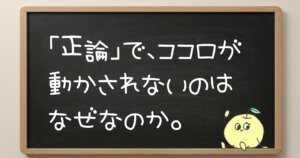感受性が高い子どもとそのサポートについて考えよう!(HSC: Highly Sensitive Child)
やぁ、ものしりんごだよ。今日は子どもたちの数ある個性のうちのひとつ「HSC: Highly Sensitive Child」について学んで行こう!
HSCとは、生まれつき感受性が高く、非常に敏感で繊細な気質を持つ子どものことを指すんだ。
これは病気や障害ではなく、個性の一つと考えられているよ。アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士によって提唱された概念で、人種や男女に関係なく、人口の約20%(5人に1人)がこの気質を持っているとされているんだ。
具体的に言うと、どんな素質を持っているとされているの?
いい質問だ!HSCの特徴は、頭文字をとって「DOES(ダス)」という4つの特性に分類されるみたいだよ。
- D (Depth of Processing) – 物事を深く考え、徹底的に処理する
- 物事を深く考え、少ない情報から多くのことを推測する。
- 結果を想像しすぎるあまり、行動に移すまでに時間がかかる。
- 間違いを恐れて、新しいことに挑戦することを躊躇しがち。
- O (Easily Overstimulated) – 過剰に刺激を受けやすい
- 光、音、匂い、触覚などの五感から入る刺激に人一倍敏感。(味の違い、室温の変化)
- 人混みや騒がしい場所を苦手とし、疲れやすい。
- 服のタグや縫い目、素材の肌触りを嫌がることがある。
- E (Emotional Responsiveness and Empathy) – 感情の反応が強く、共感力が高い
- 他人の感情や雰囲気を敏感に察知し、自分のことのように感じてしまう。
- 他人が叱られているのを見て、自分が怒られているように感じることがある。
- 芸術や音楽に深く感動する豊かな感性を持つ。
- S (Sensing the Subtle) – ささいな刺激を察知する
- 周囲の小さな変化によく気がつく。
- 相手の表情や声のトーンのわずかな変化も読み取る。
- 残酷さや不公平さ、無責任さに気づきやすい。
わ、ぼくはとっても当てはまるかもしれない!花火の音とか、すごく苦手だったよ。
でも、なんで生まれながらにして、こんなに生きづらい素質を持ってしまっているんだろう…
それはね?生物の「種族保存の原理」と深く結びついていると考えられているよ。
種族が生き残るためには、大胆で豪快な人たちだけでは不可能なんだ。危険を察知する能力と共感力が高く、深く思考し最善の選択をすることができる賢者が必要だったんだ。
だから、そんなに卑屈にならなくてもいい。HSCも、かつてHSCだった大人も、言い換えるのなら、生まれながらに「めちゃくちゃ頭がよくて、共感能力が高く、信頼できる素質」をもっているとも言えるんだ。
だからもし、上記のような素質が当てはまると感じるならそれは、きみが「可能性を秘めた大賢者」であるといって差し支えないだろう。
おお…なんだか勇気が湧いてきた…気がするぞ…
でもこの可能性を開花させるためには、肯定的な自己理解に加えて、周囲のサポートが重要になる。ポケモンで例えるなら、きみはギャラドスになる前のコイキングなわけだ。
……イーブイでもいいかな?
……。
HSCはその繊細さゆえに、生きづらさを感じることがある。だから次のようなサポートがとっても重要になってくるよ。
- 安心できる環境を整える: 刺激の少ない、静かで落ち着ける場所を用意してあげる。
- 感情を言葉にする手伝いをする: 子どもが自分の気持ちをうまく表現できないときに、「悲しいんだね」「悔しいんだね」と代弁してあげることで、自分の感情を理解しやすくなる。
- 得意なことや長所を認める: 感受性の高さや共感力は、HSCの大きな強み。そうした長所をポジティブに捉え、積極的に褒めることで、自己肯定感を育む。
- 無理強いをしない: 子どものペースを尊重し、急かしたり、他と比較したりしない。
- 完璧を求めない: 完璧主義になりがちなHSCの子どもに「完璧でなくても大丈夫だよ」と伝えることで、心の負担を軽減できる。
……。と、巷で書かれているのを目にするが、ここからがものしりんごのターン!!
実際はこうした言動の裏を見透かしてくるのが真のHSC。小手先のテクニックだけじゃ、うまくいかないことが多いのだ。理屈をこねる専門バカと怪しい教育評論家はすっこんでろィ。
……ねぇ、イーブイでもいぃ?
……。
たとえば、きみが、完璧主義なHSCのコイキングだとする。そこで親ギャラドスにこう声を掛けられるんだ。「完璧じゃなくても大丈夫よ~いいのよ~」……きみだったらどう感じる?
……そうだね。ぼくがもし、完璧主義なHSCのイーブイだったら、「はっ否定されてる!!」って思うかもしれないし、「完璧じゃなくてもいいよ」という言葉自体がプレッシャーになるかもしれない。大丈夫という言葉もなんだか曖昧で、「どうすればよかったのかなぁ」って悩んじゃうかもしれないブイ。
そう!さすがだね!もう君は、賢者という名の滝を登り終える直前かな!レベルでいうと15くらいだヨ?アメちゃん5個あげるねっ☆
……さて、もう一歩踏み込むと、わかってきたことがあるね!少し一般化すると、「サポートにおける言葉の両義性」の壁を認識することが大事なんだ!
サポートする側は「良かれと思って言った善意100%の言葉」でも、感受性の高い子どもたちは無意識のうちに、僅かな表情や声色からその裏を直観的に読み取ってしまうんだ。
…あるある!その推測が合っているか、間違っているかはわからないけれど、邪推しちゃうこともあるかも。
感受性の高さゆえに、身の回りの情報が洪水のように押しよせる。それらを深く大量に処理する能力に長けているから、絶え間ない情報処理が、脳と心にとって大きな負担となって疲れとして表れてしまうこともあるんだ。
処理せずに「ほげぇ~☆」としていられれば、いいのだけど、未解決情報がもたらす不快感や不安がその情報を放っておけない。「なんで?」「どうして?」という物事の背後を探求しようとする思考がやまないのだ。そして、意味を見出すことはHSCにとって、安心感につながる。
じゃあ具体的には、どういうサポートが必要なのかな?
そう!!「具体的」それが、HSCのサポートのキーワードのひとつなんだ。
わぁ、びっくりした…
まずは前提として、HSCへの正確な理解。HSCの子どもを「一人の賢い人間」として、真摯に向き合う態度が不可欠だ。彼らの感受性の高さを「困ったこと」と捉えるのではなく、「才能」として尊敬すること。そして、完璧でなくても、失敗しても、自分は愛される存在だと感じられるような絶対的な安心感(心理的安全性)を与えることが、自己肯定感を育む土台となるんだ。
そのうえで!!ようやく“具体的”なテクニックが生きてくる。例えば、
漠然とした「すごく綺麗な絵だね!」じゃなくて「この色の組み合わせが綺麗だね」と結果ではなくプロセスを意識した褒め方をする、小さな一歩を認めることが安心感につながる。
「ここまでできたら、次に進もうか」と区切りをつける。ゴールが見えない不安を解消してあげるために「完璧」という曖昧なゴールを、「ここまで」という具体的な区切りに変えることで、安心して行動できるようになるんだ。
HSCの子どもたちは、失敗を恐れて動けなくなっていることが多いから。言葉で「大丈夫」と安心させるよりも、小さな成功を積み重ねることで、徐々に自信をつけさせてあげることが大切なんだよね!
わぁ……簡単に言うなぁ……
……。そうだね。サポートって、難しいことなんだ。サポーターたちは常に「性急に結論を出さず、不確実性や謎、疑念の中にいられる能力」=ネガティヴ・ケイパビリティが求められる。サポーターは、相手の「答えのない状態」に寄り添い続けることによって、初めてその内面世界を深く想像し、本当に必要なサポートを見出す能力が求められるんだ。
……。まぁでも、「まず相手を理解し、敬意を払い、その上で具体的な言葉を丁寧に選ぶ」というプロセスは、HSCに限らず、すべての人間関係において大切なことだよね。
ここまで読んでくれただけでも、きみの知的想像力は豊かになったはずだ。…レベルでいうと5くらい上がったようじゃな。知識は解毒剤。知ることで少し不安が解消され、前進できる……かもしれない。
……最後に本日の学びをまとめておこう。